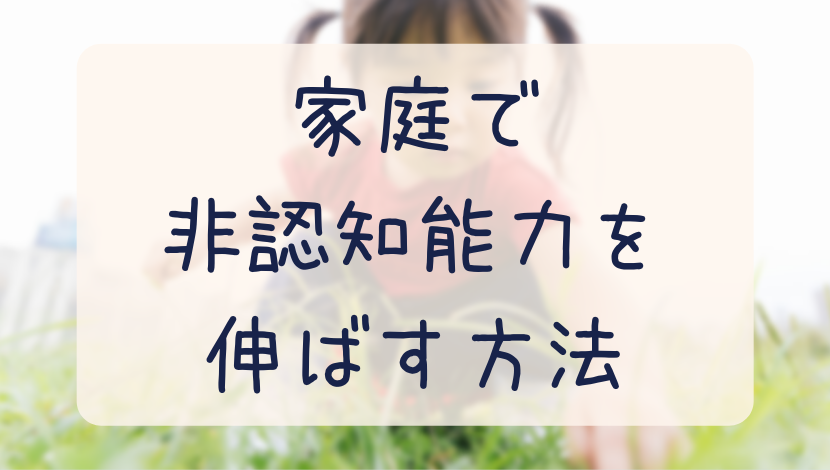「子供を将来苦労させないために、親として自分に何ができるのか」たくさん考えますよね。
私も2児の母として、小さい頃からいろいろな経験をさせて柔軟性のある子供に育てたいと思って頑張っています。
先日長男の幼稚園説明会に参加した時に、園の教育・保育目標の話がありました。
その際に非認知能力を身に着けるという説明がありました。
非認知能力を幼少期の頃から身につければ、大きくなってから社会的、経済的成功を得られると、今世界で注目されています。
そこで本記事では非認知能力について詳しく説明していきます。
「最近非認知能力という言葉を聞くけど何のことかよくわからない」
「わが子のためにきちんと理解しておきたい」
こういった疑問に答えます。
この記事を読むことで
非認知能力を伸ばす方法
を知ることができます。非認知能力と聞くと非常に難しい感じがするかもしれませんがそんなことはありません。
日常生活に少し工夫を加えるだけで伸ばすことができるのです。
非認知能力とは?

非認知能力とは、目標に向かって頑張る力、他の人とうまく関わる力、感情をコントロールする力などを指します。
詰め込み教育などでは得ることができない、厳しい場面の経験や集団など、豊かな経験により鍛えられる能力です。
逆に、数がわかる、字が書けるなど、IQなどで測れる力を「認知能力」と呼びます。
2000年にノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマン氏によると、「非認知能力」を幼少期から伸ばすことで、大人になってからの幸せや経済的な安定につながる、といわれています。
私たちは、「計算ができる・文字が読める」などの「認知能力」ばかりを重要視しがちですが、それと同じように「非認知能力」も重要です。
こういった、目標に向かって頑張る力、他の人とうまく関わる力、感情をコントロールする力は一生残ります。
その子の財産として、社会で成功する力につながります。
家庭でできる非認知能力の育て方
非認知能力は家庭で子供と関わる中で少し意識すれば簡単に伸ばすことができます。
やりたがることをやらせる
子供の自発的な部分を大事にしてあげましょう。
「○○がやりたい」と訴えてきたらやらせてあげる・何も言わずに新しいことを始めても、まずは口出しせずに見守ってみるなど、親がしてあげられることもたくさんあります。
「させられる」のではなく「自分からする」中で育ちます。
幼児期は特に「遊び」です。子供の仕事は遊ぶことだとよく言いますがまさにその通りです。
自由に遊ぶことで「やる気、意欲、粘り強さ、探求していく力、考える力」が身についていきます。
自己肯定感を高めよう
自己肯定感を高めることで自信がつきます。
自己肯定感とは、「自分には価値があるんだ」「自分は愛されているんだ」といったように自分のことをかけがえのない存在だと思えることです。
自己肯定感を高める為には、とにかく子供を「褒める」です。褒められることで自分の事が認められているという実感が得られます。
いろいろな体験を共有する
親子で同じ体験をして気持ちを共感してあげることが大事です。
インターネットの世界でなく、現実の世界でリアルなコミュニケーションをとることが大事です。
相手の表情などを見ながらコミュニケーションをとることで人の気持ちを理解する力が付きます。
夢中になっている時は見守る
これは1番目の「やりたがることをやらせよう」と似ていますが、子供が夢中になっているときは余計な干渉は避けておきましょう。
「遊ぶ」とは、自分が面白そうだと興味を持った事柄に対して夢中になって、いろいろ試していく行為です。
自分の力で最後までやり抜く力を身に着けることができます。
絵本を読む
いろいろな種類の絵本を読ませましょう。
多くの種類の絵本を読むことで創造力を高めることができます。
習慣にして身に付けよう

「非認知能力」と聞くと難しそうだと感じるかもしれませんが、いざきちんと知ってみるとそうでもないのではないでしょうか。
日常の生活でできることばかりをお伝えしてきました。
「これはするべきだ」と少しでも感じたのなら、今日からでも明日からでも実践してみて下さい。
少しずつ習慣にして幼児期から非認知能力を身に着けていきましょう。